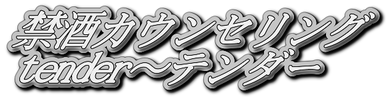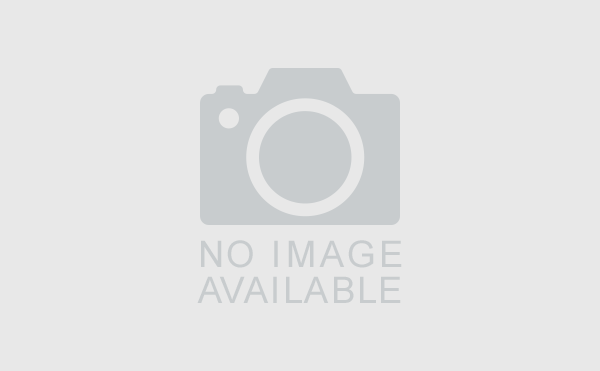お酒を飲み過ぎる人必見! 二日酔いの予防・後編!

こんにちは。
禁酒カウンセラーの溝尻啓二です。
前編では、二日酔いの原因とメカニズム、二日酔いにならないようにするにはどうしたらよいかを書きました。
後編では、二日酔にならないようにするための具体的な方法を紹介していきたいと思います。
二日酔の大きな原因のひとつは、アルコール代謝産物の「アセトアルデヒド」でしたね。
アセトアルデヒドは、アルコールを分解するときに発生する代謝産物で、毒性の強い有害物質です。
これが分解しきれず、身体の中に残ることで「もうしばらくはお酒は飲みたくない」と思わせる、あの辛い症状が出るのでした。
だから、このアセトアルデヒドをすぐに分解し、身体に溜めないようにするか、アセトアルデヒドの量を増やさないようにするのが予防策だとお伝えしました。
しかし、アセトアルデヒドの分解に大きく関係している酵素『アセトアルデヒド分解脱水素酵素』、通称ALDH2は、もともと生まれ持った体質なので、誰でもがアセトアルデヒドをすぐに分解して、身体に溜めないようにするのは難しいといこともお伝えしました。
二日酔いとはお酒を飲んだ翌日に、体内に残っているアルコールやアセトアルデヒドが原因で体調不良を起こすことです。
簡単に言ってしまえば、二日酔いの原因は基本的に、身体の処理能力を超えるアルコールを飲んだというになります。
また、いくらお酒に強い体質の人(ALDH2の活性が高い人)でも、アルコールの分解能力には限界があります。それを超えてしまえば必ず二日酔いになってしまします。
なので、お酒を『飲み過ぎなければ』防げるということになります。
「簡単に言うけど、それができたら苦労はしないよ!」という声が聞こえてきそうです………
………わかります。
お酒を飲み始めたら、いつの間にか飲み過ぎてしまっていたということは私にも経験があります。
飲み過ぎは良くない。分かっていても、お酒の力も手伝ってか、ついつい飲み過ぎてしまいますよね。
ですが、「飲み過ぎないようにする方法」のようなものを知っていれば、飲み方が少しは変わってくるのではないでしょうか?
やはり、その方法とかやり方を知らないのに、いきなり「飲み過ぎないようにしよう」としても難しいものです。
自動車の運転の仕方を知らないのに、いきなり自動車を運転しろと言われてもできるわけがありませんよね。
そんなことをすれば大事故を起こしてしまいます。
お酒もそれと同じ。
飲み過ぎないようにしようとしても、その方法ややり方を知らなければ、やはり飲み過ぎを繰り返してしまいます。
「もう飲み過ぎないようにしよう」と思っていたのにの飲み過ぎてしまったら、後悔や自責を感じてしまうかもしれません。
そんな気持ちを感じたまま「飲み過ぎ」を繰り返していたら、その気持ちを感じないようにするために「飲み過ぎないようにしよう」とすら思わなくなり、むしろ酒量が増えてしまうかもしれません。
飲み過ぎないようにすることはもちろん大事ですが、それが難しいのも私にはよくわかります。
なので、これから書く二日酔いの予防策を「守る!」すると厳しく考えるのではなく、まずは「意識」だけでもしてみてください。
それだけでもこれまでと全然違うのではないかと思います。
➀血中アルコール濃度と酔いの度合い

血中アルコール濃度というのはその名の通り、血液の中に含まれるアルコールの濃度です。
飲酒したアルコールは胃腸で吸収され、血液に乗って全身に回ることになります。
血中濃度とは「酔いの度合い」で、この数値が高くなるということは、酔いが深い状態ということ。悪酔いの原因になります。
「酔いの状態」は6段階あり、アルコールの血中濃度が上昇すると、爽快期→ほろ酔い期→酩酊初期→酩酊期→泥酔期→昏睡期の順で酔いが深くなっていきます。
それぞれ酔いの状態には以下のような特徴があります。
・爽快期………血中濃度0.02~0.04%
ビール中瓶1本、日本酒1合程度。
皮膚が赤くなり、さわやかな気分になる。陽気になる。
・ほろ酔い期………血中濃度0.05~0.010%
ビール中瓶1~2本、日本酒1~2合程度。
体温が上がる、ほろ酔い気分になる。理性が失われる。
・酩酊初期………血中濃度0.11~0.15%
ビール中瓶3本、日本酒3合程度。
立てばふらつく。気が大きくなる。大声でがなりたてる。
・酩酊期………血中濃度0.16~0.30%
ビール中瓶4~6本、日本酒4~6合。
千鳥足になる。吐き気、嘔吐が起こる。何度も同じことをしゃべる。
・泥酔期………血中濃度0.31~0.40%
ビール中瓶7本~10本、日本酒7合~1升。
まともに立てない。意識がはっきりしない。言語がめちゃくちゃになる。
・昏睡期………血中濃度0.41~0.50%
ビール中瓶10本超、日本酒1升超。
揺り動かしても起きない。大小便垂れ流しになる。死亡
一般的に1日のお酒の適量とされているのは日本酒にして1合、ビールなら中瓶1本とされています。
多くても、日本酒なら2合、ビールなら中瓶2本まで。
つまり爽快期の状態~ほろ酔い期のことを指しています。
ですが、酒気帯び運転の基準は血中アルコール濃度0.03%~です。なので、たとえ爽快期の状態でも車両を運転すれば飲酒運転となるので、酒を飲んだのならば絶対に運転はしないようにしてください。
また、合コンやコンパ等で場を盛り上げるために行われる「イッキ飲み」も大変危険な行為です。
というのも、お酒をイッキ飲みした場合、血中アルコール濃度が急激に上昇してしまうので爽快期やほろ酔い期を飛び越えて、一気に泥酔期や昏睡期の状態にまで進んでしまうからです。
これがいわゆる急性アルコール中毒です。
実際にまだ私がアルコール依存症だった頃、よく焼酎を生で飲み、間髪入れずにビールや缶酎ハイなどを一気に飲んでいました。
そして実際に爽快期やほろ酔い期を実感することなく、泥酔期の状態まで進んでいました。
昏睡期の状態に近いところまでいったこともあります。
幸いにも死亡することはありませんでしたが、危険な行為だったのは間違いありません。
このような無茶な飲酒やイッキ飲みは急性アルコール中毒から死へと繋がる危険な行為です。何かが起こってからでは遅いので、飲酒運転同様絶対にしないでください。
二日酔いは基本的に、体の処理能力超えるアルコールを飲んだことが原因で起きます。
そうならないためにも、「酔いの度合い」や、自分自身の適量を知っておくというのは大きな助けになります。
いちど飲みながら、「これが爽快期か」「なるほど、これがほろ酔い期なんだな」とか自己観察してみるのも面白いかもしれません。
そうやっているうちに、「なるほど、この酔いの程度なら二日酔いにならないな」と思えたなら素晴らしい事です。
自分にとっての適量、明日に残らない飲み方に気づけたという事です。
➁血中アルコール濃度の上昇を遅らせる

お酒を飲んで、最初に吸収されるのは胃です。
ですが、それはアルコール全体の5~10%程度で、残りの90~95%は小腸で吸収されます。
小腸に送られたアルコールは一気に吸収されるため、急激に酔いを深めてしまいます。
急激に酔いが深まればどういう状態になるのかは前の記事で言った通りです。
つまり、二日酔いを防ぐためのコツは、アルコールの血中濃度を急激に上げないようにすることなのです。
血中濃度が上がるという事は、酔いが回るということです。悪酔いの原因にもなります。
酔いが回れば、理性的ではいられなくなります。さらに血中濃度があがれば、気持ち悪くなったりフラフラしたり、嘔吐したり、まともに立てなくなったりします。
こうなってしまったら、もう二日酔いは避けられないでしょう。
では、アルコールの血中濃度を上げなようにするには具体的にどうしたらよいのでしょうか?
思い出してください。アルコールは最初にどこで吸収され、そのほとんどはどこで吸収されるのだったでしょうか?
そうです。アルコールは胃でも吸収されますが、そのほとんどは小腸で吸収されるのでしたね。
ということは、アルコールをできるだけ長く、胃に留めて、小腸に行く時間を遅らせられればいいということです。
空きっ腹でお酒を飲むと、普段よりも酔いが速く、悪酔いしてしまったという経験はありませんか?
それは、胃が内容物を消化するまで留めてくれるのは固形物の場合のみだからです。お酒のような液体の場合、胃を素通りしてダイレクトに小腸に流れ込んでいってしまいます。
なので、アルコールを胃の中に留めておくためにも、お酒を飲む前に、できるだけ消化に時間のかかる食べ物を食べるようにするといいでしょう。
胃の中に少しでも食べ物が入っていれば、アルコールの吸収は穏やかになり、二日酔いを防ぐことができます。
➂胃に長く留まる食べ物を食べる

悪酔いや二日酔いを防ぐには、血中アルコール濃度を急激に上げないこと。つまり、酔いが回るのをどうやって遅らせるかがカギになるというのをお伝えしてきました。
酔いが回るのを遅らせるには、いかにしてアルコールを胃の中に長く留めて、小腸に送る時間を遅くするかがポイントだということを理解していただけたと思います。
そのためには空腹でお酒を飲まない。お酒を飲む前に、食べ物を胃の中に入れておくのがいいという事も分かってもらえたと思います。
じゃあ、具体的に何を食べればいいのか? ということですが、胃の中に留まる時間は食べ物によってかなり異なります。
量によっても異なりますが、日本人の主食であるお米は約2時間、お肉などのタンパク質は約3時間、バターなどの油物は約12時間以上かかります。
つまり、お酒を飲む前に油物を摂ると、アルコールを長時間胃の中に留めることができます。
想像すると実感していただけると思いますが、油物は胃にもたれるイメージがありますよね。
胃にもたれる=胃の中に長く留まるという感じです。
とはいえ、油を直飲みするのは流石に抵抗ありますよね(笑)。
もちろん、そんなことをする必要はありません。
要は、油を使った料理を先に食べると良いわけですから、マヨネーズを使ったポテトサラダやオリーブオイルを使ったカルパッチョなどでも良いわけです。
たんぱく質と脂質を多く含むチーズなども消化吸収されにくいのでお勧めです。
油を使った料理の定番である唐揚げや、フライドポテトなども胃の中に留まる時間が長いといわれています。
また、飲み会の前にポテトチップスを食べていくなどするのも良いでしょう。
お酒と混じり合って半固形になるものだと、余計に腸に送られる時間が長くなります。満腹感も得られるため飲むペースが抑えられるという効果も期待できます。
ただ、注意点として油分の多いおつまみはカロリーも高いので食べ過ぎに際十分気を付けて下さい。
➃食前、食中、食後と意識しておつまみを選ぶ
お酒を飲むとき、私たちは自分が食べたいものや、お店のお勧めでメニューを決めてしまいがちです。
自分の好きなものでお酒を楽しむのも悪いものではありませんが、すこしおつまみ選びを意識してみるだけで、あの「しばらくお酒は飲みたくない………」と後悔するほどの辛い二日酔いは軽減させることができます。
食前は、前の記事で書いた通りで、空腹でお酒を飲まないようにする。飲む前に胃に何か入れておく。油を使った前菜を食べる。ポテトサラダやチーズなどがお勧めです。
食中は、たんぱく質、ビタミンB1、食物繊維を多く含む食品を選ぶようにしてみましょう。
この3つは飲酒と非常に相性が良く、食中はこれらをバランスよく食べることで二日酔いの軽減に大きく貢献してくれます。
たんぱく質

たんぱく質は、体内で最終的にはアミノ酸に分解されて吸収され、そして肝臓へ運ばれます。
アミノ酸は肝臓でのアルコール代謝を助けたり、解毒作用を促進するなど肝機能を高める効果があります。
豚肉や、牛肉、鶏肉といった結構ガツンと食べれるもので多く摂取できます。
たんぱく質はとくに意識しなくても、焼きとりなどのおつまみが出れば大量に摂取出来てしまいますね。
ですが、肉類ばかりでカロリーが気になるという人もいらっしゃると思います。
その場合は大豆をはじめとした植物性たんぱく質を選ぶと良いです。
納豆などが代表格です。
納豆の特徴であるあのネバネバが胃の粘膜を保護してくれるので、飲み過ぎた翌日に起こりがちな胃の不快感を緩和してくれます。
ビタミンB1

アルコールを体内に残さない為に欠かせないのが、実はビタミンB群です。
特にビタミンB1はアルコールを分解するときに大量に消費されます。
アルコールの大量摂取でビタミンB1が不足してしまうと、翌日の疲労感が増してしまいす。
なぜなら、ビタミンB1は糖質の代謝を助け、エネルギーを作り出すのに欠かせない栄養素だからです。
ビタミンB1が不足してしまうと、糖質をいくら摂取しても、エネルギーに変えることができませんので、疲れもたまりやすくなってしまうのです。
そうなると肝臓や腎臓の機能も低下し、胃腸障害を起こす原因にもなります。
余分に摂取してもビタミンB1は尿と一緒に排出されるので過剰摂取になることはありません。
ですので、お酒を飲んでいるときは勿論、飲んだあとも積極的に摂取したい栄養素ですね。
ビタミンB1が多く含まれる食品は豚肉、うなぎ、たらこ、ナッツなどです。
食物繊維

食物繊維は飲酒中に非常に有効な食品成分です。
食物繊維は消化されることなく大腸まで届く食品なため、チーズ同様、胃に留まる時間が長いのです。
そのため、アルコールの吸収を穏やかにしてくれる効果があります。
お酒を飲んでいるときは食物繊維を多く含むおつまみを選んでみてはいかがでしょうか?
もちろん、胃に長く留まるため、飲む前に食べる食品としても最適です。
代表的な料理としては、きんぴらや切干大根のお浸しなどです。
これらはお店でもお通しとしてよくでてくるメニューですね。
そのほか、食物繊維が多く含まれる食品は、
トウモロコシ、大豆、あずき、おから、サツマイモ、こんにゃく、ごぼう、セロリ、キャベツ、白菜など。
果実なら、かんきつ類(みかん、グレープフルーツ)、バナナ、ウリ類。
他にもワカメ、寒天、ところ天、しいたけ、しめじ、えのきなどにも多く含まれています。
特におすすめは納豆で、納豆は食物繊維とたんぱく質の両方を摂取できると同時に、あのネバネバ成分が胃の粘膜を保護もしてくれます。
➄上昇してしまった血中アルコール濃度はすぐには下がらない

これまでの記事で、酔いを遅らせることの大切さと、その助けになる食べ物はわかっていただけたと思います。
でも酒席が進むと、血中アルコール濃度が上昇することは避けられません。
上昇してしまった血中濃度をできるだけ早く下げて、悪酔いや二日酔いにならないようにする方法が知りたいですよね。
ですが残念ながら、お酒を飲んで上昇してしまったアルコール濃度をすぐには下げることはできません。
尿を出しても、汗をかいても、お酒がすぐに抜けるという事はないのです。
ですが、肝臓での代謝を助ける成分を摂ることで、二日酔いの予防対策はできます。
その成分とは、タウリン、L-システイン、セサミンなどです。
タウリン

タウリンは身体の中でも大変重要な働きをするアミノ酸です。
私たちの身体は、体内の状態を一定に維持できるように調整する機能があります。
それをホメオスタシス(恒常性維持)と呼びます。
タウリンはこのホメオスタシス作用を持っているので、体内の機能が働き過ぎることを制御したり、機能低下した時には改善させたりなど、身体が常に一定の生理作用の中で働くようにバランスをとってくれます。
アルコールは肝臓で酵素によって分解されて、毒性物質のアセトアルデヒドになります。
二日酔いの頭痛や吐き気は、このアセトアルデヒドが分解されず身体に残ることでおこる中毒症状です。
タウリンはアルコールの分解で機能が低下した肝臓の酵素の働きを助ける効果があります。
肝臓の酵素の働きを助けて、アセトアルデヒドの分解を早めてくれるのです。
近年の研究では、タウリンがアルコールの分解で生じる酢酸と結合して、尿からも酢酸を排出するという新たな作用が見つかったようです。
タウリンが多く含まれる食材は魚介類です。
カニ、イカ、タコ、エビや、カキ、サザエ、シジミなどです。
その他にもアジやサバにも多く含まれています。
またタウリンは水によく溶けるため、お吸い物や煮物にして、その煮汁も一緒に食べるようにすると効果が一層高まります。
二日酔いにはシジミの味噌汁とよく言われますが、理に適っているということですね。
L-システイン

非必須アミノ酸のひとつで、皮膚や髪、爪などに含まれるたんぱく質ケラチンの構成成分です。
アルコールを分解してできるアセトアルデヒドと反応して無毒化してくれる働きがあります。
他にも黒色メラニンの発生を抑制する効果もあります。
そのため、二日酔い予防はもちろん、美白、肌や髪のトラブル改善などの目的で健康食品としても販売されています。
コンビニなどの健康食品コーナで目にする機会も多いです。
食品から摂取しようとした場合、ブロッコリーやニンニクといったものに含まれていますが、その含有量は少量で、必要量を食事から直接摂取するのは難しいとさえ言われています。
ですがこのL-システイン、実は直接食事から摂取する必要もなく、体内合成できるので、その成分になるメチオニンを摂ってあげればいいわけです。
メチオニンを多く含む食品は大豆、鶏肉、ホウレン草、カツオ、イワシなどです。
これらで補ってあげれば、L-システインの合成量を増やすことができます。
飲酒前にL-システインを摂取したところ、摂取しなかった場合と比べて飲酒後の胃内のアセトアルデヒド濃度が60%低下したという研究も発表されています。
上記のように、幅広く市販の健康食品として販売されていますので購入も簡単な割には効果は高めなので、お酒を飲む際には積極的に利用されてみてはいかがでしょうか?
セサミン

セサミンには、アルコール代謝促進作用の他、コレステロール低下作用、血圧低下作用、脂質代謝改善作用、自律神経改善作用、疲労改善作用が期待できると言われています。
セサミン自体には酸化を抑える作用はないのですが、体内で代謝される過程で抗酸化活性をもつ代謝物に変換されます。
セサミンは一般的に健康食品などのサプリメントからしか摂取出来ないと思われている方が人が多いように感じますが、実は、普通の食品からでも摂取できる栄養素なのです。
セサミンが一番多く含まれている食品、それはゴマです。
すりゴマや練りゴマにはゴマと同じ量のセサミンが含まれています。
また、ごま油にはセサミンの一種であるゴマグリナンとセサモールも含まれています。
セサモールにもセサミン同様の強い抗酸化作用があります。
なので、お酒の席でセサミンを摂ろうとする場合ごま油をつかったおつまみ等を食べるとよいでしょう。
練りゴマやすりゴマを振りかけてある料理もお勧めです。
➅飲酒中はこまめな水分補給を

飲酒中は、とにかく喉が渇きます。
そのひとつに、おつまみによる塩分過多があげられます。
お酒に合うおつまみはとにかく塩分含有量が多いものです。
なちなみに厚生労働省が定めるナトリウム(塩分)の1日当たりの摂取目標量は、男性で8グラム未満、女性で7グラム未満です。
これはたった数品のおつまみだけでも軽く超えてしまう量です。
塩分過多になってくると、血中のナトリウム濃度が高くなります。そうすると腎臓は水分を増やして血液を正常な濃度(0.9%)に戻そうと、脳に指令を出します。
これが、塩辛いものを食べていると、やたらと喉が渇いて水が飲みたくなる原因です。
お酒を飲んでいる人は、ここで水ではなく、アルコールに手を伸ばしてしまいがちです。
私の知り合いにも「ビールがチェイサー替わりだ!」と言って憚らない豪のものがいますが、アルコールは水分ではありません(笑)。
液体なので水分補給になると勘違いしてしまいがちですが、アルコールは利尿剤です。
アルコールで脳の抗利尿ホルモンが抑制されてしまうので、必要以上に尿が出ていってしまいます。
実際にビールを飲んだ後の尿の量は、実際に飲んだ量よりも多く、1・5倍になるとの研究結果も出ています。
尿が何度も大量に出るからと「アルコールが排出されてるんだ! まだ飲めるぞー!」と喜んでいる場合ではありません。
お酒を飲んでいて、その量が減ってきたのならそれは脱水症状のサインです。
二日酔いの大きな原因のひとつに、脱水症状が上げられます。
アセトアルデヒドの代謝には水分が必要不可欠なのですが、水分補給をせずにアルコールを摂り続けていると、身体の水分量はどんどん減り、脱水症状になってしまう危険があるのです。
脱水症状の状態ではアセトアルデヒドを分解するどころではありません。
結果として、お酒がいつまでも残り、あの嫌な二日酔いの症状が長く続くことになります。
ちなみに、最初にお話しした私の知り合いも、飲み会の次の日はほぼ二日酔いでグロッキー状態です。
アルコールだけでも脱水を進めるのに、ここに塩分による乾きが加わるわけです。
身体はますます水分を要求するのですが、ここで喉の渇きを潤わせるためにアルコールを飲んでしまうと、脱水症状は更に深刻になります。
アセトアルデヒドが分解できなくなり、二日酔いへまっしぐらです。
そうならないためにも、「飲酒中は、喉が渇いたら水を飲む」を意識してみて下さい。
イギリスのNHS(国民保健サービス)でも飲酒時の水の重要性、水の活用法を推奨しています。
・時間あたりのアルコール量を制限する
・ゆっくり飲む
・食べ物と一緒に飲む
・水やノンアルコールドリンクと、お酒を交互に飲む参考・イギリスNHS(国民保健サービス)
水を飲むことで胃の中のアルコールの濃度を薄めて下げる効果もありますし、肝臓がアルコールを分解するときに必要な水分の補給にもなります。
また、水を間に挟むことで自然と飲むペースも遅くなり、結果として飲みすぎの防止にもなります。
お酒の飲み過ぎの結果が二日酔いなのですから、飲むペースが遅くなるこれらの方法は非常に理に適っているといえます。
そして、食中はもちろん、食後にもお酒の分解で失った水分を補給するのを忘れずに。
飲酒後は上記のようにアルコールの利尿作用も働いて脱水状態になっている場合が多いものです。
水分補給は、体内の水分維持効果のある電解質が含まれている経口補水液等が効果的です。
➆水のがぶ飲みには注意
水を飲むことは確かに必要なのですが、ただがぶ飲みすればいいというわけではありません。
問題はその量です。
大量に水を飲んでしまうと、血中のナトリウム濃度が必要以上に薄まってしまうため低ナトリウム血症を招いてしまう恐れがあります。
低ナトリウム血症になると、虚脱感や食欲不振、悪心などの症状が出る場合があります。
せっかくの飲み会で、こんな症状になるのは御免こうむりたいですよね。
水とお酒の量は同じくらいで丁度いいといわれています。
実際に日本酒造組合中央会でも、お酒を飲む際には水も一緒に飲むことを推奨しています。
それによれば、摂取する水は酒と同程度が理想とのことです。
⑧まとめとして

いかがでしたでしょうか?
お酒が好きな人は、お酒を飲み始めると箸が止まってしまう人が多いのではないかと感じます。
私の知り合いも、つまみはパセリと塩だけでいいという人がいました。
事実、私もその口でした。
私の場合はさらに悪く、おつまみは煙草という最悪の組み合わせでした。
そして、おつまみをほとんど食べないお酒がメインの飲み会の後は、決まって吐き気と頭痛を伴う激しい二日酔いになっていました。
ほとんどおつまみも食べず大量のお酒だけを飲んでいたため、急激に血中アルコール濃度が上がり、悪い酔いしてしまっていたのです。
悪酔いしてしまったら、理性なんて働きません、もうその場のノリでさらに酒量が増えてしまいます。
記憶が無くなるまで飲んでしまい、次の日は起き上がれないほどに苦しい二日酔い………。
皆さまの中にも、空腹でお酒を飲んで、痛い目にあった人の方が多いのではないかと思います。
思い出してみて下さい。
そのときは空きっ腹でお酒を飲んでいませんでしたか?
ほとんどおつまみを食べない、お酒が主体の飲み方をしていませんでしたか?
水分の補給を怠っていませんでしたか? あるいは、ビールをチェイサー替わりにしていませんでしたか?
それらをほんの少し改善するだけで、二日酔いの予防になりますし、飲み過ぎていると感じる人は節酒できるようになるかもしれません。
➀飲酒前に、胃に何か入れておく。最初から油物はきついという人には、チーズがお勧め。
➁たんぱく質、ビタミンB1、食物繊維の豊富なおつまみを選ぶ。
➂タウリン、セサミン、L-システインを多く含むおつまみを摂取して肝臓のアルコール代謝を助ける。
➃飲酒中は常に水を飲むようにする。量はお酒と同じ程度が理想
➄飲酒後は経口補水液など電解質を含んだ飲料水で水分補給をする。
ついついお酒を飲み過ぎてしまっているという人は、この5つをまずは意識してみてはいかがでしょうか。
前編と後編にわたって二日酔いの予防の記事を書いてきましたが、こうすれば必ず二日酔いにならない、ということはありません。
バランスよくおつまみを食べながら、最初はゆっくりと、そして自分の体調と相談しながら酒量を決めていくことが一番の二日酔い予防になります。
厳守すると堅苦しく考える必要はありません。まずは意識だけでもしてみるといいと思います。
お酒は大量に「飲む」ものではなく、楽しく美味しく「味わうもの」。そう意識してみるだけでも、きっと飲み方は変わってくるはずです。